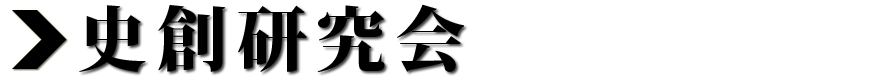安倍晋三的改憲論・覚書
小路田泰直|posted on 17 October, 2017
はじめに
2017年5月、安倍晋三総理大臣が突然支持者を前に独自の憲法改正案を示し、2020年までのその実現を宣言した。しばらく止まっていたかに見えた憲法改正への動きが一挙に動き始めた。
ただ多くの人を驚かせたのは、その発表の唐突さだけではなかった。安倍の示した改憲案が、2012年に自民党の示した改憲案とは、似ても似つかぬ改憲案であったことであった。憲法9条の1、2項を残したまま、第3項に自衛隊を合法化する項目を付け加えるというものであった。一方で陸海空3軍の不保持をうたったまま、自衛隊の合憲性だけを明確化しようというのである。それでは相変わらず自衛隊の軍隊として曖昧さは残ってしまうではないか、自衛隊は陸海空3軍とは違うといい続けなくてはならないではないか、との批判が噴出するのは必然の、改憲案であった。
しかも従来から自民党は、自衛隊は合憲だといい続けてきた。そして今や大方の国民もそれを受け入れている。だとすれば憲法第9条に自衛隊の項を付け加え、自衛隊の合憲性をより明瞭にしたからといって、何が変わるものでもない。なぜこんな中途半端な改憲案を安倍は持ち出すのだろうか。多くの人がそう思い、驚いた。うがった見方をすれば、確かに何も変えないのであれば護憲派の抵抗も弱まり、その懐柔もし易くなる。安倍は、内容の如何を問わず、ただ憲法を変えるという実績だけを残したいから、かかる改憲案を提示したのではないかとの見方さえ生まれた。
Ⅰ 安倍改憲論と「戦後70年談話」
しかしはたしてそうだろうか。今回の安倍改憲論は、それほど軽薄な動機で生み出された改憲論なのだろうか。
私はそうは思わない。むしろ今回の安倍改憲論こそ、実は戦後自民党が一貫して追い求めてきた改憲論ではなかったのかと思うのである。むしろ2012年の自民党草案の方が、例外的ではなかったのかと。
ではなぜそう思うのか。そこで我々は一つの政治的文書に注目しておかなくてはならない。それは戦後70年を記念して安倍の発表した次の談話(「70年談話」)である。長文になるが引用しておくと次の通りである。
終戦七十年を迎えるにあたり、先の大戦への道のり、戦後の歩み、二十世紀という時代を、私たちは、心静かに振り返り、その歴史の教訓の中から、未来への知恵を学ばなければならないと考えます。
百年以上前の世界には、西洋諸国を中心とした国々の広大な植民地が、広がっていました。圧倒的な技術優位を背景に、植民地支配の波は、十九世紀、アジアにも押し寄せました。その危機感が、日本にとって、近代化の原動力となったことは、間違いありません。アジアで最初に立憲政治を打ち立て、独立を守り抜きました。日露戦争は、植民地支配のもとにあった、多くのアジアやアフリカの人々を勇気づけました。
世界を巻き込んだ第一次世界大戦を経て、民族自決の動きが広がり、それまでの植民地化にブレーキがかかりました。この戦争は、一千万人もの戦死者を出す、悲惨な戦争でありました。人々は「平和」を強く願い、国際連盟を創設し、不戦条約を生み出しました。戦争自体を違法化する、新たな国際社会の潮流が生まれました。
当初は、日本も足並みを揃えました。しかし、世界恐慌が発生し、欧米諸国が、植民地経済を巻き込んだ、経済のブロック化を進めると、日本経済は大きな打撃を受けました。その中で日本は、孤立感を深め、外交的、経済的な行き詰まりを、力の行使によって解決しようと試みました。国内の政治システムは、その歯止めたりえなかった。こうして、日本は、世界の大勢を見失っていきました。
満州事変、そして国際連盟からの脱退。日本は、次第に、国際社会が壮絶な犠牲の上に築こうとした「新しい国際秩序」への「挑戦者」となっていった。進むべき針路を誤り、戦争への道を進んで行きました。
そして七十年前。日本は、敗戦しました。
戦後七十年にあたり、国内外に斃れたすべての人々の命の前に、深く頭を垂れ、痛惜の念を表すとともに、永劫の、哀悼の誠を捧げます。
先の大戦では、三百万余の同胞の命が失われました。祖国の行く末を案じ、家族の幸せを願いながら、戦陣に散った方々。終戦後、酷寒の、あるいは灼熱の、遠い異郷の地にあって、飢えや病に苦しみ、亡くなられた方々。広島や長崎での原爆投下、東京をはじめ各都市での爆撃、沖縄における地上戦などによって、たくさんの市井の人々が、無残にも犠牲となりました。
戦火を交えた国々でも、将来ある若者たちの命が、数知れず失われました。中国、東南アジア、太平洋の島々など、戦場となった地域では、戦闘のみならず、食糧難などにより、多くの無辜の民が苦しみ、犠牲となりました。戦場の陰には、深く名誉と尊厳を傷つけられた女性たちがいたことも、忘れてはなりません。
何の罪もない人々に、計り知れない損害と苦痛を、我が国が与えた事実。歴史とは実に取り返しのつかない、苛烈なものです。一人ひとりに、それぞれの人生があり、夢があり、愛する家族があった。この当然の事実をかみしめる時、今なお、言葉を失い、ただただ、断腸の念を禁じ得ません。
これほどまでの尊い犠牲の上に、現在の平和がある。これが、戦後日本の原点であります。
二度と戦争の惨禍を繰り返してはならない。
事変、侵略、戦争。いかなる武力の威嚇や行使も、国際紛争を解決する手段としては、もう二度と用いてはならない。植民地支配から永遠に訣別し、すべての民族の自決の権利が尊重される世界にしなければならない。
先の大戦への深い悔悟の念と共に、我が国は、そう誓いました。自由で民主的な国を創り上げ、法の支配を重んじ、ひたすら不戦の誓いを堅持してまいりました。七十年間に及ぶ平和国家としての歩みに、私たちは、静かな誇りを抱きながら、この不動の方針を、これからも貫いてまいります。
我が国は、先の大戦における行いについて、繰り返し、痛切な反省と心からのお詫びの気持ちを表明してきました。その思いを実際の行動で示すため、インドネシア、フィリピンはじめ東南アジアの国々、台湾、韓国、中国など、隣人であるアジアの人々が歩んできた苦難の歴史を胸に刻み、戦後一貫して、その平和と繁栄のために力を尽くしてきました。
こうした歴代内閣の立場は、今後も、揺るぎないものであります。
ただ、私たちがいかなる努力を尽くそうとも、家族を失った方々の悲しみ、戦禍によって塗炭の苦しみを味わった人々の辛い記憶は、これからも、決して癒えることはないでしょう。
ですから、私たちは、心に留めなければなりません。
戦後、六百万人を超える引揚者が、アジア太平洋の各地から無事帰還でき、日本再建の原動力となった事実を。中国に置き去りにされた三千人近い日本人の子どもたちが、無事成長し、再び祖国の土を踏むことができた事実を。米国や英国、オランダ、豪州などの元捕虜の皆さんが、長年にわたり、日本を訪れ、互いの戦死者のために慰霊を続けてくれている事実を。
戦争の苦痛を嘗め尽くした中国人の皆さんや、日本軍によって耐え難い苦痛を受けた元捕虜の皆さんが、それほど寛容であるためには、どれほどの心の葛藤があり、いかほどの努力が必要であったか。
そのことに、私たちは、思いを致さなければなりません。
寛容の心によって、日本は、戦後、国際社会に復帰することができました。戦後七十年のこの機にあたり、我が国は、和解のために力を尽くしてくださった、すべての国々、すべての方々に、心からの感謝の気持ちを表したいと思います。
日本では、戦後生まれの世代が、今や、人口の八割を超えています。あの戦争には何ら関わりのない、私たちの子や孫、そしてその先の世代の子どもたちに、謝罪を続ける宿命を背負わせてはなりません。しかし、それでもなお、私たち日本人は、世代を超えて、過去の歴史に真正面から向き合わなければなりません。謙虚な気持ちで、過去を受け継ぎ、未来へと引き渡す責任があります。
私たちの親、そのまた親の世代が、戦後の焼け野原、貧しさのどん底の中で、命をつなぐことができた。そして、現在の私たちの世代、さらに次の世代へと、未来をつないでいくことができる。それは、先人たちのたゆまぬ努力と共に、敵として熾烈に戦った、米国、豪州、欧州諸国をはじめ、本当にたくさんの国々から、恩讐を越えて、善意と支援の手が差しのべられたおかげであります。
そのことを、私たちは、未来へと語り継いでいかなければならない。歴史の教訓を深く胸に刻み、より良い未来を切り拓いていく、アジア、そして世界の平和と繁栄に力を尽くす。その大きな責任があります。
私たちは、自らの行き詰まりを力によって打開しようとした過去を、この胸に刻み続けます。だからこそ、我が国は、いかなる紛争も、法の支配を尊重し、力の行使ではなく、平和的・外交的に解決すべきである。この原則を、これからも堅く守り、世界の国々にも働きかけてまいります。唯一の戦争被爆国として、核兵器の不拡散と究極の廃絶を目指し、国際社会でその責任を果たしてまいります。
私たちは、二十世紀において、戦時下、多くの女性たちの尊厳や名誉が深く傷つけられた過去を、この胸に刻み続けます。だからこそ、我が国は、そうした女性たちの心に、常に寄り添う国でありたい。二十一世紀こそ、女性の人権が傷つけられることのない世紀とするため、世界をリードしてまいります。
私たちは、経済のブロック化が紛争の芽を育てた過去を、この胸に刻み続けます。だからこそ、我が国は、いかなる国の恣意にも左右されない、自由で、公正で、開かれた国際経済システムを発展させ、途上国支援を強化し、世界の更なる繁栄を牽引してまいります。繁栄こそ、平和の礎です。暴力の温床ともなる貧困に立ち向かい、世界のあらゆる人々に、医療と教育、自立の機会を提供するため、一層、力を尽くしてまいります。
私たちは、国際秩序への挑戦者となってしまった過去を、この胸に刻み続けます。だからこそ、我が国は、自由、民主主義、人権といった基本的価値を揺るぎないものとして堅持し、その価値を共有する国々と手を携えて、「積極的平和主義」の旗を高く掲げ、世界の平和と繁栄にこれまで以上に貢献してまいります。
終戦八十年、九十年、さらには百年に向けて、そのような日本を、国民の皆様と共に創り上げていく。その決意であります。
平成二十七年八月十四日
内閣総理大臣 安倍 晋三
興味深いのは、この文章に、戦後日本に対する価値否定がないことである。むしろ「国際社会が壮絶な犠牲の上に築こうとした「新しい国際秩序」への「挑戦者」となっていった」戦前日本を明瞭に批判している。しかも次のように述べ、そうなっていく日本に歯止めをかけることのできなかった「国内の政治システム」をも厳しく批判している。1930年代を単なる「過誤」「逸脱」とはみていないのである。
当初は、日本も(その「新しい国際秩序」をつくるのに・小路田)足並みを揃えました。しかし、世界恐慌が発生し、欧米諸国が、植民地経済を巻き込んだ、経済のブロック化を進めると、日本経済は大きな打撃を受けました。その中で日本は、孤立感を深め、外交的、経済的な行き詰まりを、力の行使によって解決しようと試みました。国内の政治システムは、その歯止めたりえなかった。こうして、日本は、世界の大勢を見失っていきました。
高らかに
二度と戦争の惨禍を繰り返してはならない。
事変、侵略、戦争。いかなる武力の威嚇や行使も、国際紛争を解決する手段としては、もう二度と用いてはならない。植民地支配から永遠に訣別し、すべての民族の自決の権利が尊重される世界にしなければならない。
先の大戦への深い悔悟の念と共に、我が国は、そう誓いました。自由で民主的な国を創り上げ、法の支配を重んじ、ひたすら不戦の誓いを堅持してまいりました。七十年間に及ぶ平和国家としての歩みに、私たちは、静かな誇りを抱きながら、この不動の方針を、これからも貫いてまいります。
かく謳い揚げている点は、日本国憲法前文にも通じている。
かかる「談話」が僅か2年前に安倍の口から発せられたのである。そのことに我々は留意すべきである。だとすれば今回のような改憲案が安倍の口から出たとして、そこに何の不思議もない。そして安倍といえば祖父岸信介を限りなく崇敬する自民党改憲派の主流である。「今回の安倍改憲論こそ、実は戦後自民党が一貫して追い求めてきた改憲論ではなかったのか」との私の仮説は、あながち間違いでもなさそうなのである。
Ⅱ 安倍改憲論の生まれる歴史的必然
ではなぜ日本の保守派は、今回の安倍案のような改憲案を持つに至ったのだろうか。押し付け憲法批判を繰り返してきた彼らのイメージからはほど遠い案を、である。そこで見ておきたいのは、安倍の祖父岸信介らの抱いた戦争観である。岸といえば「2キ3スケ」と呼ばれた、満州国の建設とその開発に大きな役割をはたした5人の指導者の1人であり、東条英機内閣で商工大臣を務め、まさに彼なくして国家総動員体制はつくれなかったといわれるほどの人物である。だから彼は極東国際軍事法廷(東京裁判)において、最後は不起訴になったが、A級戦犯容疑をかけられたのである。ちなみに「2キ3スケ」とは星野直樹、東条英機、鮎川義介、松岡洋右、岸信介の5人のことであった。何れもが満州事変に始まり「大東亜戦争」にいたる15年にわたる戦争の肝心要の所で決定的な役割をになった人物たちであった。
では岸が抱いた戦争観とは。「2キ3スケ」を満州に誘った人物、まさに謀略によって満州事変をひき起こした人物、石原莞爾の「世界最終戦論」であった。それは次のような戦争観であった。
① 一番遠い太平洋を挟んで空軍による決戦が行われる時が、人類最後の一大決勝戦の時であります。即ち無着陸で世界をぐるぐる廻れるような飛行機ができる時代であります。それから破壊の兵器も今度の欧州大戦で使っているようなものでは、まだ問題になりません。もっと徹底的な、一度あたると何万人もがペチャンコにやられるところの、私どもには想像もされないような大威力のものができねばなりません。飛行機は無着陸でグルグル廻る。しかも破壊兵器は最も新鋭なもの、例えば今日戦争になって次の朝、夜が開けて見ると敵国の首府や主要都市は徹底的に破壊されている。その代わり大阪も、東京も、北京も、上海も、廃墟になっておりましょう。すべてが吹き飛んでしまう……。それぐらいの破壊力のものであろうと思います。そうなると戦争は短期間に終わる。……このような決戦兵器を創造して、この惨状にどこまで堪え得る者が最後の優者であります。(「最終戦総論」『最終戦争論』所収)
② 戦争には二つのことが大事です。一つは敵を撃つこと――損害を与えること。もう一つは損害に対して我慢することです。即ち敵に最大の損害を与え、自分の損害に堪え忍ぶことであります。この見地からすると、次の決戦戦争では敵を撃つものは少数の優れた軍隊でありますが、我慢しなければならないものは全国民となるのです。今日の欧州大戦でも空軍による決戦戦争の自信力がありませんから、無防備都市は爆撃しない。軍事施設を爆撃したとか言っておりますけれども、いよいよ真の決戦戦争の場合には、忠君愛国の精神で死を決心している軍隊などは有利な目標ではありません。最も弱い人々、最も大事な国家の施設が攻撃目標となります。工業都市や政治の中心を徹底的にやるのです。でありますから老若男女、山川草木、豚や鶏も同じにやられるのです。かくて空軍による真の徹底した殲滅戦争となります。(「最終戦争論」)
③ 兵器の発達が世の中を太平にしているのです。この次の、すごい決戦戦争で、人間はもうとても戦争をやることはできないということになる。そこで初めて世界の人類が長くあこがれていた本当の平和に到達するのであります。要するに世界の一地方を根拠とする武力が、全世界の至るところに対し迅速にその威力を発揮し、抵抗するものを屈服し得るようになれば、世界は自然に統一することとなります。(「最終戦争論」)
まずは「世界の一地方を根拠とする武力が、全世界の至るところに対し迅速にその威力を発揮し、抵抗するものを屈服し得るようになれば、世界は自然に統一する」、即ち1つの超大国の軍事的支配下に世界をおくことができれば、世界に恒久平和をもたらすことができるとする考え方であった。第二次大戦後のパクスアメリカーナのような体制の実現をもって最終的な理想とする考え方であった。
しかし、その1つの超大国を生み出すためには、幾つかの超大国候補の国々の間におっける、「無着陸で世界をぐるぐる廻れるような飛行機」と「一度あたると何万人もがペチャンコにやられるところの」「破壊の兵器」(大量破壊兵器)を用いた「すごい決戦戦争」――「最も弱い人々、最も大事な国家の施設が攻撃目標とな」る「老若男女、山川草木、豚や鶏も同じにやられる」「空軍による真の徹底した殲滅戦争」――が必要になる。「世界最終戦論」とは、その1つの超大国を生み出すための「殲滅戦争」を積極的に肯定する戦争観であった。積極的に肯定するから、その「真の徹底した殲滅戦争」を、各国が「自分の国の利益のために戦う」通常の戦争とは区別し、「世界人類の本当に長い間の共通のあこがれであった世界の統一、永遠の平和を達成する」ための聖戦とみなし、次のように「両方の選士が出て来て一生懸命にやる」「武道大会」に喩えたのである。
今は国と国との戦争は多く自分の国の利益のために戦うものと思っております。……私はそんな戦争を、かれこれ言っているのではありません。世界の決勝戦というのは、そんな利害だけの問題ではないのです。世界人類の本当に長い間の共通のあこがれであった世界の統一、永遠の平和を達成するには、なるべく戦争などという乱暴な、残忍なことをしないで、刃に血刃(ちぬ)〔編集部注:血へんに刃〕らずして、そういう時代の招来されることを熱望するのであり、それが、われわれの日夜の祈りであります。しかしどうも遺憾ながら人間は、あまりに不完全です。理屈のやり合いや道徳談議だけでは、この大事業はやれないらしいのです。世界の残された最後の選手権を持つ者が、最も真面目に最も真剣に戦って、その勝負に勝って、その勝負によって初めて世界統一の指導原理が確立されるでしょう。だから数十年後に迎えなくてはならないと私たちが考えている戦争は、全人類の永遠の平和を実現するための、やむを得ない大犠牲であります。
われわれが仮にヨーロッパ組とか、あるいは米州の組と決勝戦をやることになっても、断じて、かれらを憎み、かれらと利害を争うものでありません。恐るべき残虐行為が行なわれるのですが、根本の精神は武道大会に両方の選士が出て来て一生懸命にやるのと同じことであります。人類の文明の帰着点は、われわれが全能力を発揮して正しく堂々と争うことによって、神の審判を受けるのです。(「最終戦争論」)
ちなみにその「すごい決戦戦争」に日本が参戦するための物質的条件を得るために石原らの始めた戦争が、満州事変であった。ロシアが未だ革命の混乱の中にあり、アメリカが恐慌対策におわれている間に満州を占領し、その経済開発をはかることで、日本もその「すごい決戦戦争」に参加できるだけの国力を身につけようとしたのである。
そしてこうした戦争観をもったからこそ、石原やその信奉者たち(「2キ3スケ」)は、満州事変に始まる15年間の戦争を戦い抜いたのである。彼らにとって、満州事変に始まる15年間の戦争は、どのフェーズをとってみても、決して「自分の国の利益のために戦う」戦争ではなかった。即ち侵略戦争ではなかった。どこまでも、世界に恒久平和をもたらすための「聖戦」の一部だったのである。安倍の使った表現を用いると、「国際社会が壮絶な犠牲の上に築こうとした「新しい国際秩序」への「挑戦者」」になりたくて彼らは戦ったのではなかった。むしろその積極的な「建設者」たらんとして戦ったのである。
ではかかる戦争観をもった人たちにとって敗戦と、その結果おきた日本のパクスアメリカーナへの組み入れ――具体的には日本国憲法体制と日米安全保障条約体制の「強制」――はどう映ったのだろうか。
自ら望んだ結果と映ったのではないだろうか。それが証拠にというべきか石原莞爾は、敗戦の玉音放送が流れた、まさにその日(1945年8月15日)に、東亜連盟会員に対して次のようなメッセージを送っているのである。
二、平和条約を有利にするための方策。
1 敵進駐に先だち次の改革を断行、敵を驚嘆せしむ。
(1) 国民輿論による軍閥政治の打倒を実現す。軍は進んで内面よりこれに策応し、直ちに果敢なる復員を行い、「軍人勅諭に反し政治に干与するに至りし罪」を天下に謝し、軍備を撤廃す。
次代の軍備は今日の陸・海・空軍と全然、異なれるものなること疑いなく、一時の撤廃は却って、その再建設のための有利なり。
(2) 日本は世界一の「民主主義」国なることを明らかにす。国体は「君主主義」「民主主義」を超越せる存在なり。日本の民主主義は官権主義に対するものにして、官僚専制の打倒は刻下の急務なり。(「敗戦の日に東亜連盟会員に訴う」『最終戦争論』所収)
まさに日本国憲法第9条の先取りであった。
しかもある段階――もしかしたら開戦以前――から、彼等が「世界最終戦」の勝者になることよりも、敗者になろうとそれを戦い抜くこと自体を目的にし始めたことは明らかであった。「生きて虜囚の辱を受けず」と記した「戦陣訓」の策定や、「特攻」や「玉砕」など、死の美学の追究は、その現れのように思われる。ならば彼らにとって、敗戦と、日本国憲法体制であれ、日米安全保障条約体制であれ、パクスアメリカーナの受け入れは、決して望まざる結果ではなかったことになる。戦後岸らの主導した改憲の流れが、鳴り物入りの表向きとは異なり、決して過激に走らなかった所以である。
そして安倍は、この石原や「2キ3スケ」の精神的後継者なのである。ならば彼が日本国憲法の基本的な枠組みを変えることなく憲法改正を試みたとしても、それは決して不自然なことではなかったのである。
Ⅲ 安倍自民党はなぜ改憲に固執するのか
こうしてみてくると、安倍改憲案が第9条に3項(自衛隊条項)を付け加えるだけという、憲法全体には殆ど手をつけない改憲案になる理由はわかる。しかしだとすれば逆に分からなくなるのは、なぜ自民党や安倍は、無理に無理を重ねて憲法改正に固執するのか、そちらの方の理由である。
そこで大事なのは、石原莞爾や「2キ3スケ」の精神的後継者である安倍でさえ、満州事変に始まる15年間の戦争を総括するにあたっては、次のようにいわざるをえなかったという現実の存在である。
満州事変、そして国際連盟からの脱退。日本は、次第に、国際社会が壮絶な犠牲の上に築こうとした「新しい国際秩序」への「挑戦者」となっていった。進むべき針路を誤り、戦争への道を進んで行きました。
それを「国際社会が壮絶な犠牲の上に築こうとした「新しい国際秩序」」形成の努力の一環とは、間違ってもいえないことである。石原らにとって、国家が「国の利益のために戦う」のではなく、世界に統一と平和をもたらすために、それに必要な1つの超大国を生み出すために戦う「世界最終戦争」は、勝者になろうと敗者になろうと、参戦すること自体に意味のある聖なる戦争であった。だからこそそれを「憎み」を超えた、「正しく堂々と争うことによって、神の審判を受ける」「武道大会」に喩えたのである。
しかし勝者はこの論理に従わなかった。勝った自らを自由と民主主義の守り手(正義)とし、負けたドイツや日本を悪逆非道な侵略者(不正義)に貶めたのである。石原や「2キ3スケ」のあらゆる努力は、「国際社会が壮絶な犠牲の上に築こうとした「新しい国際秩序」への「挑戦者」」の営みとして、否定しさられたのである。
ならば求めて得たはずの日本国憲法体制や日米安全保障条約体制も、強いられて組み入れられた屈辱の体制ということになってしまう。300万人の犠牲者も「英霊」から「犬死にせしもの」に変わってしまう。それにはさすがに石原や「2キ3スケ」や、その後継者たちには耐えられなかった。だから彼らは日本国憲法体制や日米安全保障条約体制を、自ら求めた体制として、再定位しなくてはならなくなったのである。1960年に岸が日米安全保障条約を改定し、その相務条約化をはかったのも、そのためであった。
そしてそうなったとき、ポツダム宣言第12項には次のようにあった。
前記諸目的が達成せられ且日本国国民の自由に表明せる意思に従ひ平和的傾向を有し且責任ある政府が樹立せらるるに於ては、連合国の占領軍は、直に日本国より撤収せらるべし。
ならば、独立する以上、憲法の見直しをすればいいということになったのである。これが、私が思うに、自民党結党以来、石原や「2キ3スケ」の後継者たちが、自主憲法制定に固執するようになった原因であった。また、だから憲法改正には常に第二次大戦の評価の見直しという問題が関係してきたのである。
むすびに
では安倍改憲案はこのまますんなりと成立するのだろうか。私にはまだ幾つかのハードルが残されているように思える。
一つは、あくまでも第二次大戦を、ファシズム対反ファシズム、帝国主義対反植民地主義の戦いとみなそうとする世界からの反発――歴史修正主義批判の嵐――がある。その反発を跳ね返し、第二次世界大戦を、石原莞爾がいう意味での「世界最終戦」と認めさせるだけの歴史観の「創造」が必要になる。
そして今一つは、第二次世界大戦が日本にとっても、パクスアメリカーナの創出を目的に――アメリカの超大国化を助けるために――、負けを覚悟で戦った「聖戦」であったといったときにおこる、国民の反発がある。時に理在らずして負けたとしても、勝つための犠牲であれば、300万人の犠牲も我慢できる。しかし最初から負けるための犠牲として、300万人の命が供せられたとすれば、それを国民は我慢できない。その国民の反発がある。
石原や「2キ3スケ」のその複雑な戦争目的に対する反発があるから、戦後日本国民は二派に分かれたのである。一つは、日本国憲法を絶対的平和主義の福音の如く受け止め、政府の起こす如何なる戦争にも無条件に反対する派。政府の喧伝する戦争目的に対する絶対不信がその形成を招いた。通常左派、リベラル派と呼ばれる人々である。そしてもう一つは、やはり敗戦を敗戦として素直に受け止め、何とか敗戦の屈辱を振り払い、日本の国家としての独立を達成しようとする派である。岸や安倍ほど凝ったことを考えない、通常の自主憲法制定派である。独立国に相応しい完全な再軍備と、日本国憲法体制からの完全な脱却を求める。2012年の自民党改憲草案は、この派の策動の産物だったのかもしれない。現代の政治家でいえば中曽根康弘や石破茂に代表される派である。
当然この二派の撲滅は困難を極める。何れも人の自然な感情に根ざしているからである。その困難が安倍的改憲に対する最大のハードルになる。
そして思うのは、2017年秋の総選挙は、この二派を共に撲滅するための、安倍の奇策だったのかも知れないということである。小池百合子に民進党を割って新党(希望の党)を結成させることによって、民進党に寄る辺を求めていたリベラル派に決定的な打撃を与え、帰す刀で、小池との連携を模索していた石破茂ら、より純粋な保守派に対して再起不能な打撃を与えるという。
また国民が新たな「聖戦」の犠牲に供せられると思えば、何とも恐ろしい。予想のあたっていないことを祈るばかりである。
参考文献
石原莞爾『最終戦論』(経済往来社、1972年)
依田隆一・最上敏樹編修『コンサイス条約集』(三省堂、2009年)
小路田泰直『日本憲法史―八百年の伝統と日本国憲法』(かもがわ出版、2016年)
内閣府HP
林尚之「内閣憲法調査会と憲法無効論」(『寧楽史苑』第62号、2017年2月)

「柏崎刈羽原発フォーラム」に参加して
小路田泰直|posted on 27 November, 2012
第55回自治体学校in新潟プレ企画「原発依存から地域経済の再生を――柏崎刈羽原発フォーラム――」が、11月24日土曜日午後、柏崎市産業文化会館で開催され、本科研のメンバーである岡田知弘氏と川瀬光義氏が、それぞれ「原発に頼らない地域経済の再生」「原発に頼らない財政を展望する」というテーマで、約1時間ずつ講演されました。こちらも本科研のメンバーである立石雅昭氏が企画立案されたフォーラムです。
岡田氏の講演は「原発稼働停止で柏崎の事業所の4割に影響……」等々といった報道が、如何に事実に反する誇張された報道か。柏崎市とその周辺の経済は言われるほど多くは原発に依存していない事実を指摘し、原発に頼らない地域経済の再生は可能性というものであり、川瀬氏の講演は、基地を抱える自治体同様、原発を抱える自治体の財政構造が、如何に歪んだものになっているか、「電源三法交付金」の実態をもとに告発するものでした。
いずれも熱のこもった講演で、会場一杯に詰めかけた聴衆も、誰一人席を立たず、真剣にメモをとりながら聞き入っていました。
私自身も、お二人の講演を聴き、非常に勉強になりました。そして考えさせられました。
原発が、社会にとって必要かどうかはさておき、社会全体にとっては必要だが、それが立地する地域にとっては「迷惑施設」以外の何物でもないような産業や施設を、社会はいかにしてつくり出し、維持していくべきなのか、まだ答えが出ていないのだなと思いました。ましていわんや原発のように、その必要性自体が疑われ始めた施設となると、話は余計にややこしくなると思いました。
そして世界最大の原発が、なぜここ柏崎に建設されたのか、その実相の解明がますます必要となってきているとの思いを強くし、午後4時過ぎ長駆奈良への帰途につきました。

柏崎刈羽原発調査メモ
小路田泰直|posted on 14 October, 2012
これは2012年9月27日から29日にかけて柏崎刈羽原発の調査を行ったときに考えたことのメモである。
Ⅰ
2007年7月16日におきた中越沖地震をきっかけに、新潟日報社特別取材班が全力をあげて取り組んだルポタージュ『原発と地震』(講談社、2009年)に記された柏崎刈羽原発の建設と田中角栄の関わりを示す部分である。
「責任を感じている。柏崎に原発を呼んできたのは父ですし・・・・」
東京電力柏崎刈羽原発が被災した中越沖地震の発生から十日後の〇七年七月二十六日。元首相田中角栄の長女で衆院議員の真紀子(63)は新潟市のホテルで、参院選を戦う民主党候補の応援演説の中でこう語った。
同原発の建設予定地をめぐる土地売却益四億円が届けられた元首相邸。主の田中は原発誘致にどうかかわっていたのか。
地元が誘致を決議した六九年当時、自民党幹事長として抜群の政治力を示していただけに、さまざまな憶測を呼んできた。
「どこまで立ち入っていたのかははっきりしない。資源外交に努めていたのは分かるが・・・・」
原子力産業の発展を目指して五六年に設立された日本原子力産業会議(現日本原子力産業協会)の元専務理事・森一久(81)は考え込んだ。
森は原産会議に設立時から五十年間勤務した。業界の生き字引的存在だ。約五十年前にあった原子力に関する国の審議会答申内容をよどみなく語る森だが、田中が表立って誘致に動いた記憶はないという。
柏崎刈羽原発建設に携わり、同原発所長も務めた宅間正夫は推測する。
「(誘致の経緯を記した)書物で田中さんの名前を見たことはない。政治問題にさせないため、表に出るのを避けたのだろうか」
ただ、森は田中と原発との接点と考えられる人物を一人挙げた。森が長年仕え、原産会議副会長も歴任した松根宗一(故人)だ。五四年、理研ピストンリング工業(現リケン)の会長に就任すると同時に東電顧問となる。六三年に柏崎市長になったばかりの小林治助(故人)に原発誘致を勧めた人物である。
松根は愛媛県宇和島市出身。日本興業銀行に勤めた後、理研に入った。電力業界でつくる電気事業連合会副会長にも就いた。「電力業界生え抜き以外の副会長は松根さんの後にも先にもいない」と森。屈指のエネルギー事業通だった。
森は、松根と田中が同席した場面に一度だけ立ち会ったことを覚えている。田中は「松根さん。娘(真紀子)をもらってくれる人が決まって本当に良かった」と喜んでいたという。だが、原子力の話はなかった。
森は「松根さんは『今日、角さんがこんなことを言っていた』とよく私に話してくれた。二人は非常に親しかった。自宅も近かった」と振り返り、原発誘致に関する推測を口にした。 「どちらかというと松根さんが勧め、田中さんが話に乗ったのではないか」
田中の地元筆頭秘書を務め国家老と呼ばれた本間幸一は松根との面識はないと言う。
「うち(田中)と理研とのつながりはあった。東京で何かあったのかも知れないが、松根さんがどう絡んだのかは知らない」
と話し、「(田中から)原発誘致に関する指示を受けた記憶はない」とする。
参院選の演説で父角栄の誘致関与を示唆した真紀子。しかし、発言内容を確認すると、
「周辺の人から伝え聞いただけ。父はエネルギー政策は重要とよく言っていたが、父から原発の話を聞いたこともないし、個別に話したこともない」
柏崎刈羽原発誘致に限っては具体的な動きが見えない田中。だが、首相時代の七四年六月、原発立地自治体に多額の交付金を配分する電源三法を「生みの親」として成立させ、原発推進の表舞台に立つ。田中内閣総辞職の半年前だった。
電源三法の発案者は柏崎市長・小林とされる。六九年の誘致決議を機に原発建設への行程は順調に進むかに見えた。だが、大きな試練が小林を待ち受けていた。
(73〜75頁)
田中と柏崎刈羽原発建設との深い関わりを感知しながら、結局つめきれなかったというところか。
しかし私は、本人たちの主観的評価は別として、新潟日報社特別取材班の記者たちは、相当深い所にまでことの本質に迫っていると思う。森一久との接触を通じ て、松根宗一の存在にまで迫っているからだ。記者たちは、一つのことを知らなかっただけだ。
戦後日本は、戦前以来続けてきた核開発を断念しなかった。戦時中原爆開発に従事した仁科芳雄を中心に、どんな困難があろうと、継続しようとした。核に負けたのだから。二度と核に負けるわけにいかなかったからだ。
そして1948年以降、冷戦の深まりとともに、アメリカの核の傘の中に積極的に入りながら、ということは水爆を中核兵器としたアメリカの核の傘の建設に協力しながら、自らは核の平和利用という形で、核開発を継続する道を選択した。だからアイゼンハワーが1953年12月8日国連で「平和のための核」演説をし、翌54年3月1日、南太平洋ビキニ環礁でアメリカが水爆実験に成功した翌日、3月2日、中曽根康弘らによる原子力予算2億3500万円の緊急上程が行われたのである。
その戦後日本の核開発の中核にいたのが、上記の仁科芳雄であり、彼の再建した理研だったのである。さらにいえば、軽武装独立を考えざるを得なかった宰相吉田茂であった。そして田中角栄といえば、佐藤栄作や池田勇人と並ぶ、吉田学校の異色の優等生であった。
もうわかるだろう。新潟日報記者が突き止めた田中角栄と――理研の――松根宗一のつながりの裏には、吉田茂と仁科芳雄を軸に進められた、戦後日本の核開発プログラムがあったのである。田中と松根の関係は、明らかに吉田と仁科の関係と相似形をなしていた。柏崎刈羽原発がその相似のエネルギーから生まれたことは、ほぼ確実である。
そう思えば、新潟日報の記者たちは確かに柏崎刈羽原発誕生の秘密に迫っていたのである。ただ田中=松根関係が、何を写し、何と相似していたのか、そのことへの視線がなかっただけであった。
引き継ぐのは我々である。
Ⅱ
さてそう考えると、浮かび上がってくるのは、柏崎刈羽原発の他の原発にない重要性である。それはあたかもパイロット事業のごとき位置づけをもつ原発であったことが想像できる。
そこで興味深いのは、上記引用の下線部を施した部分である。1974年に成立した電源三法(電源開発促進税法・電源開発促進対策特別会計法・発電用施設周辺地域整備法)の制定が、柏崎刈羽における原発反対運動の盛り上がりを契機にしていたとしている点である。1970年代に生まれる新たな核開発体制、電源三法体制もまた、柏崎刈羽を起点にしていたというのである。私はあり得ると思う。
それは、長年柏崎刈羽原発反対運動に携わってこられた武本和幸氏(原発反対刈羽村を守る会/柏崎原発反対同盟)にお話をおうかがいしたときに、そう確信した。おうかがいした柏崎刈羽における1960年代末から70年代にかけての原発反対運動は、確かに、時の宰相田中角栄をして心胆を寒からしめるものがあったからである。
氏によれば、1960年代末から1970年代にかけての、柏崎刈羽の原発反対運動は、原発周辺の集落(村)を舞台に、「町会」レベルで、田中の後援会組織越山会と多数を奪い合う運動だったという。だから反対派の側も、越山会組織に対抗して次のように集落毎に一つ一つ「守る会」をつくっていったのである。
1969年 荒浜を守る会 宮川を守る会
1970年 刈羽を守る会
1971年 新屋敷を守る会 椎谷を守る会
1972年 大洲を守る会 西元寺生活を守る会
1973年 正明生活を守る会 大塚生活を守る会 赤田北方生活を守る会
1974年 荒浜をよくする会
(柏崎市『原子力発電その経過と概要』2012年3月より)
それまでの労働運動や街頭闘争型の政治運動とは、全く違ったタイプの運動であった。当時高まりをみせていた公害反対運動と共通性の高い運動であった。公害反対運動は、常に公害によって直接被害を被る極限された小地域の人々の、生活に根ざした命の叫びの運動としての特徴をもつ。だから容易に広がらないが、逆に力強い。その種の運動であった。
だからそれは、社会の表層を流れていくタイプの運動ではなく、越山会のような自民党の強固な保守基盤を突き崩す可能性を秘めた運動だった。自民党の総帥田中角栄の心胆を寒からしめても決しておかしくない運動だったのである。
しかもそれは、既存の二つのエリート集団に「方向転換」を迫る程の勢い示した。一つは二大政党の一翼を形作る日本社会党であった。社会党は「60年安保」の敗北を契機に、発展期から停滞期、後退期に入っていた。結局万年野党を脱し得ずに終わろうとしていた。労働運動に依存し、街頭闘争を繰り返すだけの運動の限界だった。その社会党にとって、公害反対運動や原発反対運動のもつ保守地盤に食い込む力は魅力に映ったに違いないのである。社会党が、1972年1月26日の党大会で「原子力発電所・再処理工場の建設反対運動を推進するための決議」を行ったのは、その帰結であった。
この社会党の「方向転換」にも、柏崎刈羽の原発反対運動は、直接大きな影響を与えていたと思われるのである。今後の検討課題だが。
そしてもう一つのエリート集団は「知識人」「学生」であった。彼らもまた「70年安保」が不発に終わる中、革命幻想の終焉に直面していた。代わる闘争の舞台を求めていたのである。したがって三々五々原発反対運動の周辺に蝟集してきたのである。しかもそこは彼らの活動舞台として適していた。彼らの専門家としての能力が縦横に発揮できる舞台だったからである。
武本氏は、原発反対運動に、外からの「知識人」「学生」の応援が如何に大きな役割をはたしたかを語ってくれた。武谷三男(物理学者)、水戸厳(物理学者)、末田一秀(原子力防災)、小出裕章(原子力工学)、今中哲二(原子力工学)などの名があがった。
以上、柏崎刈羽の原発反対運動のインパクトが、田中角栄に電源三法体制を選択させた可能性は十分にあった。上記『原発と地震』の推量は、的を射ていた可能性が高いのである。
Ⅲ
そして田中にとって本当に深刻だったのは、社会党や「知識人」「学生」の反原発への「方向転換」であった。それは明らかに55年体制の蹉跌を意味していたからであった。保守・革新が、憲法9条や再軍備の可否をめぐっては争っても、平和利用に名を借りた核開発では手を握るというのが、戦後日本を支えた安全保障体制であった。それにひびが入ったからであった。
当然田中が、電源三法を制定し、原発の立地が、地域の保守基盤の崩壊につながることを何とか防ごうとしたのは、その55年体制に入ったひびを修復するためでもあった。
だから田中にとって、電源三法の制定は、それだけで単独の施策にはならなかった。社会党――及び社会党的なるもの――を抹殺した新たな戦後政治体制(保守二大政党制)の構築が、それと連動していたはずである。彼が策して失敗した小選挙区制の制定が、彼の愛弟子小沢一郎によって1993年に実現され、それがこの国の政界の保守二大政党制への再編のきっかけになったことを考えれば、そういえそうである。
その点についての検討、それも今後の我々の課題である。
〔参考〕
樫本喜一「公害・環境問題と原子力問題―見えない連鎖反応」小路田泰直編『福島第1原発事故誤報道資料集』(2011年度奈良女子大学研究推進プロジェクト経費研究成果報告書)2012年3月
拙稿「ヒロシマからフクシマへ」『史創』№1、2011年8月
「安全神話の政治学」『史創』№2、2012年3月