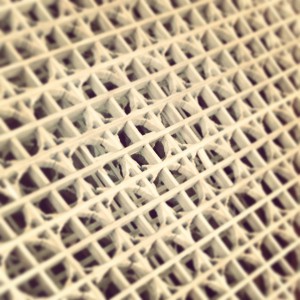物体をどこまでも分割していく。するといずれは、これ以上は分割できない小さな物体があらわれるだろう。それをデモクリトスは《原子》といった。これは哲学上のひとつの立場であって、無際限に分割できるという立場もありうるが、ともかく実感しやすいものである。というのも、たとえば紙を手でどんどん細かく引き裂いていくとき、手の大きさに依存した限界が訪れることは明白だからである。しかし、原子という考え方がありうるなら、この哲学上の立場を拡張して、時間を分割していくとあらわれる最小の時間という概念もありうるかもしれない。それをひとびとは《刹那》と呼んでいるように、わたしには思われる。
◆
ジャック・デリダは、近代、あるいはプラトンの時代からはじまっているという「音声中心主義」を批判していた。彼のいわゆる音声中心主義、それは、おのれの語る声は、おのれの精神と自己同一的であるという、じつは根拠のない仮定をもとにした、西洋形而上学に特有とされる態度である。しかし、音声には、かならずそれを聞く者が存在する。それを発する口に対して、それを取り入れる耳がある。「自分が―話すのを―聞く」。一見、自己同一的にみえるこの円環のなかに、彼は差異を見出す。この差異を、時間的な延長の意味を込めて「差延」と呼ぶ。音声中心主義は、差延を隠蔽し、内なる他者の、小さくはかない声を黙殺する。わたしの観点からいえば、「自分が―話すのを―聞く」という円環のなかで見出される話す自分と聞く自分とを区別する時間的差異こそ、最小の時間的単位としての《刹那》である。
この観点は、たとえば自民族中心主義を批判できる。たえず内なる他者に耳を傾けるこの観点は、安易な自己同一化を許さず、差異に耐え抜くことを要求する。それはかまわない。問題は、この観点のおかげで、独白がまったく存在できなくなることである。あらゆる独り言を、誰かの耳がたえず聞いている。すなわち、他者であるところのおのれの耳が。自民族中心主義を非難できるのはよいことだが、独白さえ他人が聞いているような国家では、言葉は衰退していかざるをえない。というのも、小声の呟きまで残らず社会化されるような国家とは、自民族のなかだろうが他民族に対してであろうが、とにかく犯罪者を作りだすことが容易な国家でもあるからである。その本質からいって、鼠や猿よりも、蛙や鳥、蝉や蟋蟀に似ている人間は、その特性上、なかなか沈黙することができない。だから、迂闊な思いつきを口にすることさえ憚られる社会において、人間は、おのれが《取るに足らない》者であることを証明するのに躍起になり、ますますくだらないことばかり喋るようになる。差延を可能にする円環のなかで、外部の他者はきわめて遠い存在となろう。おのれの声は、差異を孕んだこの円環から出ることができなくなる。かつて矢の姿をしていた言葉は、円環のなかでとぐろを巻く蛇に変身する。この蛇は人間を騙すことしかしない。たえず孕まれている差異を隠し、かりそめの自己同一性をひとに信じ込ませることしかしない。シニフィアンであるところのおのれの声と、シニフィエであるところのおのれの精神とは、たえず(つねに―すでに)齟齬しており、声はおのれの精神を欺きつづける。そう訴えることが、《差延国家》において罪を逃れる唯一の方策であるように思われる。悪いのは人間ではない、言葉だ。言葉は衰退させられるべき代物なのだ……。
◆
いかにして価値であるような独白は可能なのか。独白の定義は簡単である。他人が聞いていないことではない。他人が言葉を聞くかどうかは偶然に任されていることである。しかし、定義の簡単さにくらべて、独白を可能にするハードルは高い。それは一般的な意味での他人が存在しない場所をみつけだすのが難しいからではなく、《刹那》によって区別される内なる他者は、必然的に存在しているように思われるからである。純粋な独白を可能にするためには、おのれの言葉を耳にするおのれが存在できないような仕組みを考えださねばならない。しかし、それはほとんど不可能であるようにみえる。口と耳の距離は確実に存在するからである。にもかかわらず、われわれは、差延の哲学を乗り越えて、なんとしてでも純粋な独白を実現しなければならない。それだけが、来たるべき国家に対する来たるべき人間の唯一の抵抗となることが、ほぼ確実だからである。
ひとはおのれの声を聞く。差異として聞こうと自己同一性のうちに聞こうと、ひとはすでに差延の泥沼に足を突っ込んでいる。デリダはこの議論を音声に限定したが、声であろうと文字であろうと、それは生じている。自分の書いた文字を読むという行為が、ここ十数年のあいだにきわめて一般化されてきている今日では、より顕著となっていよう(文字の場合は、文字を書くおのれの手と、それを読み取るおのれの眼球とが作る距離が、差延を形成している。これは根拠のない憶測だが、光の速度と音の速度の差異は、眼球と手、耳と口の距離の差異に比例しているかもしれない)。
ひとつのありそうな解決策は、《刹那》を越えて時間は無際限に分割できると考える立場を取ることである。そうすれば、話すおのれと聞くおのれの差異はいずれ抹消できるだろう。しかし、この立場には難点がある。というのも、《刹那》を形成する口と耳の距離は、精神的なものというより肉体的なものだからである。無際限に分割できるという観点は、無限にかかわる以上、有限の肉体にかかわるというより精神的なものである可能性が高いから、この立場で時間的差異を抹消しても、差延は残ってしまう。むしろたんに、肉体上の差異が隠蔽される結果になる恐れがある。したがって、肉体あるかぎり、《最小の時間は存在する》。《刹那》は保持されねばならない。
◆
わたしはここまで、差延と《刹那》を曖昧に扱ってきた。だが、これからはできるだけ明確に区別することにしよう。個体の内部で発生する精神的時間にもとづく差異を「差延」と呼び、《刹那》は肉体的・物理的な時間の最小単位に充てる。というのも、デリダの概念は、どう考えても内部と外部の質的区別を前提しており、しかももっぱら差延は精神的なものとして扱われているからである。たとえば人種と異なる「民族」は、血液よりも歴史によって定義される。差延の指摘が自民族中心主義を否定できるなら、それは自動的に精神上の問題に向けられていることを意味している(その点を敷衍していうと、重力のように純粋に物理的に定義された概念を差延によって覆すことは困難だろう)。というか、差延こそ精神なのだ。おそらく、《刹那》はかえって独白の条件となるだろうはずのものである。
さて、いまやとるべき方策はひとつしかなかった。《刹那》を細分化し抹消することは、死ぬか、精神の世界に引きこもるか、そのいずれかをしないかぎり、われわれには不可能である。したがって、生きている人間にできることは、肉体的・物理的な《刹那》を保持しつつ、精神的な差延を抹消することである。すなわち、世界を内部と外部に分割し、内部を防衛する(=外から隠す)皮膚を取払い、皮膚によって可能になる屈折した精神を発生させないようにすることである。皮膚のなかにあるのは、精神ではない。脳や神経、心臓である。肉のなかには肉がある。ある種の――たとえばレオナルド・ダ・ヴィンチのような――解剖学者のように、精神を肉に生成させ、同じことだが、外部に投擲したおのれの声のうちに、精神を残らず投げ渡すことである。小林秀雄の表現を借りれば、自意識の球体を破砕することであり、もっと簡単にいえば、《自分の欲望に正直に語ること》である。内部を裏切る外部、外部を裏切る内部。内と外とを分つ皮膚を取り払うなら、言葉は欲望と等しくなる。そのときにだけ、言葉は独白の権利を得る。
◆
独白とは、どのような言葉だけが、そう言われうるのか。――内部と外部とによって形成されるおぞましいほどねじれた円環を切断すれば、時間は一本の矢となる。言葉はそこでは、共有することのできぬ《刹那》によって分たれた彼岸の住人に向けて飛ぶ、一本の矢となる。矢は時間を過去と未来とに切り分けながら飛ぶ。矢は内から外に向けて放たれる――というより、矢にとって、おのれの進む方向が外である。すなわち、別の《刹那》、未来のおのれに向かって飛ぶ矢こそ、もっとも純粋な、唯一の独白である。おのれを未来のおのれに向けて跳躍させる言葉こそ、真の意味での独白である。ひとは夢を語る。現在のおのれを鼓舞し、未来のおのれに向けて語られる約束として。この約束に向けてひとが真剣に努力しているかぎり、それは独白でありつづける。そうありたいと望む言葉にむけて、おのれが努力しているとき、それこそが、唯一可能な独白なのである。