1619年11月10日、ドナウ河畔ウルム冬営の夜、デカルトは《われ》を発見した。その時、彼に一体なにが起こったのだろうか。われわれは、これを近代の始まりとみることに慣れている。近代とは、神のものでもなく、王のものでもない、《主観を中心とした合理主義》の世界の始まりである。それはカントの《純粋悟性》に、そしてヘーゲルの《概念》に変奏され、資本主義および戦争という二つの車輪をもって猛烈なスピードで回転する車軸となった。
あの夜のデカルトの発見を近代の始まりとみるその視線は、すでに反省的なものである。彼の発見は、どう考えても、近代とも、近代文学とも無関係のはずである。彼の発見を近代と結びつけているのは、端的に後世のわれわれである。だが、そのことを見えにくくしてしまうのは、彼の発見に、「ゆえにergo」が含まれていたせいである。われわれが近代の「原因」をコギトに見いだすその所作が、彼のいった「ゆえに」に転嫁されてしまうのだ。
だが、「ゆえにergo」を因果律として捉えているのは、われわれであって、彼ではない。そうした読解は、歴史主義でありすぎるし、また同時にテクスト主義でありすぎる。「ゆえに」は、彼のコギト(Cogito)の単独性を、屈折を孕んだ個別的な認識(Cognitio)に変えてしまう。
◆
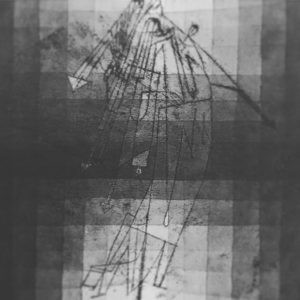
◆
われわれは、彼のコギトに、《出来事》をみる。「ゆえに」は、次の表象を導く《とand》であって、彼の「われあり」の《実感》を主体に折り返す屈折は必要がない。つまり、彼はあの夜、たしかに、出来事として存在していた(だから存在などという用語はふさわしくないし、現在を起点とする過去形もふさわしくない)。彼の猜疑心は、あの夜、ついに頂点に達した。彼の抜け目ない猜疑は、最後まで見落としていた蒙(くら)い中心、すなわち己に達したのである。彼は、消え去り、口だけの怪物になって、こう言ったのだった。
「われありとは、われ思うのなかに消え去ることだ!」
コギトとは、懐疑の完成であり、虚無(ニヒル)ではなく、真空を実現することである。ヘーゲル弁証法が頭で立っていることを発見したマルクスに習っていえば、カントのデカルト読解はさかさまである(マルクスを賞賛する多くの人が、カントの読解がさかさまであることに気づかないのはどうしたわけか)。しかし、カントのおかげで、じつは、懐疑を完遂するためには、「われ」を疑うだけでは不十分であることがわかる。「われ」は、その他の表象のように、疑うだけでは消え去ったりはしないからだ――というのも、「疑うわれ」がどうしても存在してしまう。むしろ、「われあり」を「われ思う」のなかに取り込み、存在ごと思惟のなかに抹消しなければならない(デカルトが、「われ疑う」ではなく、「われ思う」といっている点に注意しよう)。
こうした思考は、むろん、《主体=Je》ともかけ離れているし、《存在=suis》ともかけ離れている。歴史がついにたどりつくことのできないものが、すでに消え去った過去なのだとすれば、コギトは歴史とも無関係である。なぜなら、コギトとは、自ら消え去る《出来事》の謂いだからだ。痕跡を欠いた彼のコギトの真の《意味》は、歴史のなかに消え去ったのである。彼は消え去ることで、《近代》とは別のパラレルワールドを切り開いた。すなわち、《文学》の世界である。
◆
批評家や学者には、この出来事の響きは聞こえない。なぜなら、彼らは、コギトを、《読んでしまう》からだ。消え去ることのない、痕跡(あるいはエクリチュール)としてのコギトは、再認、つまりCognitioを可能にしてしまう。だが、ついにインコグニートに終わるデカルトのコギトは、消えていく声、波動の世界のなかに存在している。だからニュートンが見出した光がデカルトには見えなかった。デカルトの懐疑は、とりわけ光に向けられている。彼の猜疑が実践していたこと、それは光を色彩に変えることだった(つまり闇に色彩を見いだすことだった)。
しかし、批評家や学者、すなわち読むひとたちは、色彩を光とその影に変えてしまう。彼らは色彩に分割線を引き、認識のうちに色彩を奪取する。これがカントである。色彩は、光と影の両極に結わえられた弁証法の運動と重なる。これがヘーゲルである。結局のところ、合理主義が行なうことは、闇を影に変えることであり、光から色彩を抜き取ってしまうことであり、声を刻印されたものに換装することである。むろん、それはデカルトから始まるのではない。むしろ、デカルトのコギトを《テクストとして読んだ》者たちから始まるのである。
◆
天才スピノザ。“Ego sum cogitans”という読解が示すように、彼は、デカルトのコギトを、テクストとして読まなかった(わたしの読解とは多少異なるが)。彼は「ゆえに」を忠実に読むことを遠ざけた。なにより、デカルトに対して忠実であるために。「われ思うゆえにわれあり」が証明ではないとすれば、それはデカルトの《実感》以外のものではないし、合理的なものではありえないだろう。むしろ、「われ」に対する信仰に似通ったなにかである。デカルトを肯定し続けたスピノザが見いだしたのは、《実感の論理学》(ドゥルーズの言い方でいえば、「感覚の論理学」)、すなわち、非合理的なものの合理性である。
われわれは、非合理的なものの合理性を追究すること、こちらを《西欧合理主義》と呼ぶべきだと考える。それは、非合理的なものと合理的なものとを裁断することではないし、そんな思考は、近代西欧以外のどこにでもありふれたもので、堕落したものである。《西欧合理主義》の驚異は、むしろ、非合理的なものと合理性を完全に接合してしまったことにある。《魔法とは、科学のことだ!》 彼らは、要するに、闇に色彩を見いだしたのである。それは粒子のなかに波をみつけることであり、この別種の合理主義は、おそらく色彩と音楽とに関わっている。
◆
われわれが目ざす《出来事の学》もまた、ここにある。たとえばアルチュセールは、スピノザに非科学的なものの科学を見出した。つまり、科学的ではありえない歴史を科学する可能性を、彼に求めた。だが、われわれは、それは端的に、《文学》のことだと考える。スタイルとは、まさに感性において作動するものであり、反省的な視座から生まれる歴史とは、ついにかかわりを持たない。そのことによる利点もある。それは、主観やイデオロギーにまでは至らない、独特なものの見方、すなわち《方法》を提供することである。
スタイルにとって、歴史観やイデオロギー、そして主体は、あまりに屈折したものである。よくある誤解は、堕落した合理主義から見られたものだ。つまり、イデオロギーや主観を批判するあまり、方法まで捨て去ってしまうことである。文学的な用語でいえば、作者や主体を非難するあまり、文体まで捨て去ってしまうことである。事実を過信する、あまりに粗雑な合理主義は、たしかに最後に主体(主観)を攻撃し始める。だが、そうした攻撃は、本来味方であったはずの方法や文体まで消し去ってしまうのである(今日、「デカルト」は、こうした粗雑な堕落した合理主義の別名となっている)。その結果が今日の実証主義であり、また今日の虚構=私小説である。そこでは、真理ならぬ事実だけが散乱し、結果として、事実が真理に偽装され、巨大で不可視のイデオロギーと化してしまう。そこでは、事実を照らす報道だけがあるのだし、その反対側に、徹頭徹尾の影としての虚構がある。
しかし、歴史観やイデオロギーを非難するためとはいえ、方法まで捨て去ってはいけないし、主体や技巧を非難するためとはいえ、文体まで捨て去ってはいけないのだ。文体は、悟性や理性にまでは到達しない、感性的な刺激のうちに存在している。感覚が織りなす複雑な角度が、感情=文体を実現する。感情といっても、身体の奥深くに蓄えられたルサンチマンとは無関係である。それはいわばテニスのラケットであり、知的に研ぎ澄まされたさまざまな角度や早さが、多様な感情を実現していく。だから、感情は、感官に与えられた刺激を純粋悟性で解釈することとは無関係である。もっとすばやい。たとえば、高貴なひとは、怒りをこらえたりはしない。避けるべき怒りであれば、それをいなすのだし、仮にこらえることがあったとしても、それはあくまで、来るべき怒りを増幅させるために、敢えて行なっているのだ――たとえば、オデュッセウスのように(ニーチェがいうように、カントとは、そうした怒りをいったん悟性に蓄積し遅延させる効果のことである。また、その点からすれば、無意識とは、要するに、大脳皮質の外側にある人間の皮膚感覚のことである)。だから文体は方法同様に、主体よりもむしろ実践と結びついている(志賀直哉はいっていた、「歴史など書き換えてしまえ!」)。文体が実現するのは、言葉の色彩であり、言葉の音楽である。
文学が文体に関わるものであるかぎり、さまざまな生の技法を実現する。そしておそらく、そこにのみ意志をもつのが、純文学である。この学は、歴史とはついにかかわらないし、主体(人称)とも無関係である。むしろ、端的に、出来事の学であることを欲している。フランス語で書かれたJe penseとは、まさに、「われ」すなわち主体を抹消するための、デカルトのスタイルだったのである。
[amazon asin=”4588008781″ /]
[amazon asin=”458800879X” /]




